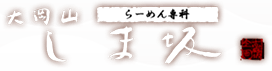閑かさや磐にしみいる蟬の声
切れ字「や」は感動の中心なんて参考書にあるけれど、
芭蕉のこの句はもともと「山寺や」であったのを、
芭蕉ほんにんが「閑かさや」に推敲したものである。
なんで感動の中心を推敲するのか、
参考書なんてあてにならないものである。
ただ、わたしがもうしあげたいのは、
句の文法ではなく、「蝉」についてである。
立石寺(どこでもかまわないけれども)で鳴くおびただしい蝉、
あれは、ほんとうに蝉だろうか、ということである。
日本国語大辞典でも「せみ」は、成虫の蝉を示しているし、
ふるく「色葉字類抄」にも「節用集」にも「せみ」はある。
平安時代から「蝉」は「セミ」とよばれていたことは自明である。
が、しかし、よくわかっていないらしいが、
蝉は地中で七年も八年も暮らしている。
そして、時かなえば、危険きわまりない地上に姿をあらわし、
まるっきりちがったカタチに変貌し、一週間の命をおえる。
そのデフォルマシオンのすがたには、口がない。
ただ一本の幹の蜜を吸う管だけだ。内臓だってない。
ほんとうに生きようとすれば、まずゴキブリのような固い顎が必要だ。
それは、わたしどもが背中に一本の酸素を
つんで宇宙に「子ども作って来いよー」と
抛りだされたようなものだ。
つまり、あれが蝉のほんとうの「抜け殻」なのだ。
木にしがみついている抜け殻は、
ほんとうの「抜け殻」をおくりだした抜け殻なのである。
ようするに、蝉の一生は地中のなかにある。
それこそそれが成虫というものだ。
種族保存のためになにがあるかわからない外界にでて、
残された時間、がむしゃらに鳴き続ける、
あれは成虫ではなく、
むしろ、死に化粧、あるいは死に体といったほうがいい。
わたしたちは、名前をつけてしまうと、
その本質を見失う。「蝉」と名付ければ、
もうあの八日目のない生き物を「蝉」とおもいこんでしまう。
奥村晃作さんの作品。
梅の木を梅と名付けし人ありて疑はず誰も梅の木と見る 『父さんのうた』
コスモスの重鎮も、名づけは本質を見失うと語るのである。
記号というものは、世界分節の差異化であると
同時にものの本質を隠蔽する機能を偶有する。
ある短歌の師匠が、いいですか、
このコップがコップでなくなるまで見つめるのです、
と語っていたが、
やはり、コップという名前をはずしてコップを
見てみなさいという教えである。そこにコップの本質があるからだ。
夏の真っ盛り、むかしの教え子と
蝉しぐれの並木道をあるくこともあるが、
そのとき、わたしは彼女にいうのだ。
「あの蝉たち、死んでるよ」