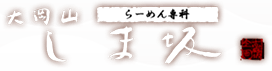「面白い」という語は
民俗学者に言わせれば
むかしは、焚火の周りに人が集まり、
それを、
ひとりの話者が周りの人に語っている姿を
遠くから見たら、炎のせいで顔だけが
白く見えた、というところから
うまれた語らしい。
『醒酔笑』などという江戸時代の書籍もある。
「笑い」というものは
ひとの本能と地続きにつながっているから
哲学的な研究材料になるだろう。
じっさい『笑いの哲学』なる書籍もある。
優越の笑い(いじりと自虐)、
不一致の笑い(あるあるとズラし)、
ユーモアの笑い(価値破壊的な笑い)
などあるらしいが、
わたしは、そんなむつかしいことを
語るわけではない。
いまの笑いは、やや劣化してきたのではないか、
わたしはそうおもうのだ。
その裏側に、芸人の芸にたいする評価のようなものが
受け手にうまれているという事情があるのではないか。
漫才にしても
グランプリ形式ものが多数うまれていて、
それに優勝したものが称賛される時代だ。
だから、見ているひとも点数をつけたがる。
細かすぎてわからないモノマネとか、
IPPONグランプリとか、
審査員的な存在が必要である。
日本エレキテル連合なんか
ひとつも面白くないのに売れていた時代があった。
そういうお笑い番組につきものなのは、
その芸に受けている、他の芸能人がいる、
ということである。
エレキテル連合の「いやよ、いやいや」を
岡村さんが満面の笑み笑っているシーンが
数秒、演技中に流れる。
つまり、わたしたちは、
みずからの演技の評価の前に、
芸能人の笑っている姿をとおして
その芸を見ているという図式ができあがっている、
ということなのだ。
直接性の笑いではなく、
芸人のフィルターを通した間接的な芸を
われわれは享受しているに過ぎない。
「これは、きっと面白いに違いない、
だって、とんねるず笑っているし、
岡村も笑っているから」
という無意識のバイアスがわれわれに
かけられているのである。
その点、たまに放映されている落語となると、
芸人と客という一体一の関係性で成り立っている。
あれこそが芸なのだ。
一席の途中で、客の笑う姿を映している
場面は一度もないが、漫才になると、
たまに客席が映し出される。
そこにいまの漫才ブームの列化と
落語という文化を担った芸との差があるのだろう。
しかし、どんな笑いにせよ、
笑うということは、
体内からペーターエンドルフィンという
物質がうまれ、これが、体内麻酔のような
はたらきがあるらしいので、
疲れの特効薬になるそうだから、
大いに笑うことがよろしい、
ということで、じゃんじゃん、終わります。